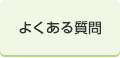いなべFM第88回令和6年9月27日放送「もの忘れ初期集中支援チームの役割・内容について」
いなべFM第88回令和6年9月27日放送「もの忘れ初期集中支援チームの役割・内容」

9月は世界アルツハイマー月間です。今回は認知症の方や、その家族を支援するもの忘れ初期集中支援チームの一員である、いなべ市地域包括支援センターの保健師の佐藤昌子さんへのインタビューです。
認知症の方が安心して暮らせることが症状の進行を遅らせます

もの忘れ初期集中支援チームの役割は、もの忘れのある方の症状の進行を緩やかにする目的で、薬による治療と薬以外でできることを伝え、生活に取り入れてもらうことです。保健師と社会福祉士で自宅を訪問し、これまでの生活や既往歴、趣味、もの忘れの程度を伺います。次に運動、人とのコミュニケーション、社会参加など、本人に合った方法を共に考えます。また、お困りの症状への対応方法、利用できるサービスの紹介や、もの忘れ専門外来の受診予約や介護保険サービスの調整支援も行います。チームには支援の方向性と方法を相談できる認知症専門医とサポート医がいます。
72歳女性Aさんのエピソードを紹介します。
Aさんは5分前のことも忘れてしまうような記憶障害がありましたが、体には不自由なところはなく、ひとり暮らしでした。近くに長男夫婦と孫が住んでいて、よくAさん宅へ来てくれていました。読書家で、地域のボランティア活動や趣味活動に積極的に参加し、友人とのランチやおしゃべりを楽しんでいました。
ある日、Aさんは、参加予定の市民講座の会場を忘れてしまい、違う会場に参加したことをきっかけに地域包括支援センターに相談され、もの忘れ初期集中支援チームが訪問しました。長男に連絡すると、家族もAさんの認知症の症状に悩んでいました。
Aさんは、もの忘れ専門外来を受診し、アルツハイマー型認知症と診断されました。要介護認定の申請を行った結果、要介護1と認定され、運動中心のデイサービスを利用することになりました。
介護サービスを開始して、2年が経過した現在も、Aさんはひとり暮らしを続けています。友人に手伝ってもらいながら四日市駅で待ち合わせて、ランチやコンサートに出かけています。ボランティア活動もおこなっており、出かけるときは、仲間から事前に連絡をもらい、活動中は周囲の方にさりげなくフォローをしてもらうことで、続けることができています。調理や金銭管理、入浴は一人では難しくなっていますが、ケアマネジャーが症状の進行に気づき、デイサービスの利用日を増やし、ヘルパーによる日常生活の援助を導入しました。ケアマネジャーは家族やボランティア仲間、友人とも連絡を取り合い、Aさんは今まで通り、地域で楽しく過ごしています。
早い遅いはありますが、誰もが若い時のままの脳ではいられず、認知症のリスクがあります。家族や友人、地域の人や趣味活動の仲間たちと、「忘れるようになったら声を掛け合おうね」「集まりを忘れていたら誘ってね」と、自分から言い合える関係が必要だと思います。
まとめ
もの忘れ初期集中支援チームでは、認知症ケアの知識を持った専門職が、もの忘れのある方の自宅へ訪問して健康状態や生活の様子を確認しながら、生活上の困りごとに対して医療や介護サービスの必要性や日常生活の支援方法などを提案します。認知症の進行を遅らせるためには、本人が安心して暮らせるような周囲の環境や支援が必要だとわかりました。
いなべ市認知症初期集中支援チームに関するお問い合わせは
いなべ市地域包括支援センター 電話0594-86-7818までお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ
福祉部 長寿福祉課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7819 ファクス:0594-86-7865
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地