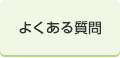いなべFM第105回令和7年6月13日放送「高齢者に起こりやすいお口のトラブル」について
いなべFM第105回令和7年6月13日放送「高齢者に起こりやすいお口のトラブル」
毎年6月4日から10日は「歯の寿命を延ばし、健康の保持増進につなげること」を目的とした「歯と口の健康週間」です。今回は 二之宮歯科医院 院長 二之宮洋平(にのみやようへい)さんへのインタビューです。
高齢者の口の健康は、さまざまな面に影響を与えます

人生100年時代を迎え、健康寿命を延ばすことがますます重要になっています。その鍵のひとつが、高齢者の「口の健康」です。口は食事や会話など、生活の基本的な機能を担うだけでなく、全身の健康にも大きな影響を与えます。
口の中の病気というと、むし歯や歯周病があります。 むし歯は、口の中にいる細菌が食べ物の糖分をエサにして増殖し、歯の表面のエナメル質を溶かしてしまう病気です。特に、高齢者は、歯周病によって歯茎が下がり、歯根が露出するため、むし歯になりやすくなります。そして 歯周病は、歯こうの中の細菌によって歯周組織が破壊される慢性的な炎症性疾患です。炎症が続くと、歯周病菌が血液を通じて全身に運ばれ、糖尿病や心疾患などの全身疾患の発症リスクを高めると考えられています。 歯周病がますます進行すると、歯を支える骨が溶けて歯が抜け落ちてしまいます。
高齢者は、むし歯や歯周病のり患率と重症度が高くなります。 これは、加齢による免疫力の低下や口くうケアの不足などが原因と考えられています。そして、歯や歯肉のトラブルばかりでなく、えん下機能の低下や唾液の減少など、口の働きにもトラブルが起こります。それが、誤えん性肺炎や口くう乾燥症と言われるものです。
誤えん性肺炎とは、食道から胃に送られるはずの食べ物や飲み物、唾液などが、主に口の中の細菌といっしょに気道内に入ってしまうことで起こる肺炎です。 高齢になると、のどの筋肉が衰え、物を飲み込む機能が低下し、発生しやすくなります。
口くう乾燥症は、唾液の分泌量が減少して口くう内が乾燥する病気です。唾液には、食べ物を飲み込みやすくし、むし歯や歯周病を予防する役割があります。加齢とともに、唾液腺が委縮して唾液の分泌量は減少します。また、舌や口周りの筋肉のカが弱くなり、かむ機能が低下することも唾液の分泌量が減少する原因となります。 そして、口くう乾燥は口臭や味覚障害、むし歯や歯周病のリスクを高めるなど、さまざまな影響を及ぼします。
高齢者の口のトラブルを防ぐためには、次の4つのことが大事です。
(1)「口くうケア」
口のトラブルを防ぐための最も基本的な方法です。 毎日のブラッシングによるセルフケアが口のトラブルを防ぐ最大の予防です。 一生おいしく、楽しく、安全な食生活を送るために口くうケアは非常に大切になります。
(2)「よく噛んで食べる」
よくかんで食べることで、消化吸収を良くし、脳への刺激にもなるため、認知症予防にもつながります。 一口30回以上を目安に、ゆっくりよくかんで食事をしましょう。
(3)「口くう機能訓練」
舌や口周りの筋肉を鍛える体操を行うことで、口くう機能の維持・向上に役立ち、口くう機能の衰えを改善できます。
(4)「定期的な歯科健診」
毎日の口くうケアはもちろんですが、健康な歯を維持するためには、定期的な歯科検診が推奨されています。
高齢者の口の健康は、全身の健康・社会生活・精神面など、さまざまな面に影響を与えます。 これら4つを実践していただき、身体だけではなく口の健康も意識することで、これからもおいしく食事をして、家族や友人と楽しく過ごしください。
まとめ
高齢者がいつまでも元気に暮らしていくためには、心身の衰えを予防することが大切です。口のトラブルを防ぐための4つのポイントを実践して、口くう内の健康が維持できると、しっかりかんでおいしく味わい、元気にしゃべって笑って健康寿命を延ばしましょう。
※インタビューの内容は趣旨を変えない程度に編集しています。
このページに関するお問い合わせ
福祉部 長寿福祉課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7819 ファクス:0594-86-7865
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地