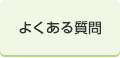いなべFM第111回令和7年9月12日放送「認知症の症状」について
いなべFM第111回令和7年9月12日放送「認知症の症状」
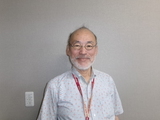
9月は「認知症月間」と定められ、認知症に対する関心と理解を深めるための様々な活動が行われます。第111回・112回は認知症について、脳神経内科の家田俊明医師にお話を伺います。今回は、「認知症の症状」についてです。
早期受診が認知症の状況の改善につながります
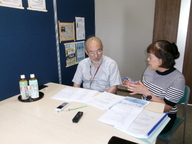
認知症とは、一言でいうと、いったん正常に発達した知能が、日常生活に支障をきたすまでに低下していく病気です。わかりやすく言うと、普通に生活していた人が、脳の神経細胞が衰えていくことによって、普段通りに仕事や家事ができなくなることをいいます。
認知症の症状としては、記憶障害がよく知られていますが、その他にも時間・場所・人物の見当がつかなくなる見当識障害や、計算能力の低下、判断力の低下、言葉の機能が衰える失語があります。また、物が見え、聞こえているのに認識できない失認や、ハサミなどの簡単な道具の使い方がわからなくなる失行、物事を計画し、効率的に実行することが困難になる実行機能障害などがあります。これらの認知機能の本質的な低下を認知症の中核症状と言います。
中核症状の進行に伴って記憶力・見当識・判断力などが低下し、本人が不安を感じる一方、その状況を打開するために他人からみると異常と思える行動(異常行動)に至ることがあります。さらに、そのような異常行動とそれに対する周囲の反応が悪循環を招き、ますます本人の不安状態が進行し、状況が悪化していくこともしばしばみられます。このように認知症の中核症状と周囲からの反応によって生まれる状態を周辺症状と言います。
最近では、周辺症状の発生要因に着目して、認知症の行動・心理症状をBPSDと 呼ぶことが多くなってきました。BPSDの具体的な症状としては幻覚、妄想をはじめ、徘徊、睡眠障害、抑うつと不安、焦燥、暴力や暴言、性的な行動などがあります。また、夕方から夜にかけて不安、混乱、帰宅願望、攻撃的行動などが増加することも多く、日没症候群、夕暮れ症候群などとも言われています。この原因ははっきりしていませんが、体内時計の変化、疲労、薬の影響などが関係すると考えられています。
軽度認知障害は、MCIとも呼ばれますが、正常な老化に比べると認知機能が低下しているものの、認知症というほど認知機能が低下していない状態のことを言います。認知症の前段階にあたるとも言えます。
軽度認知障害は、日常生活において記憶障害はあるものの、一般的な認知機能、日常生活能力はほぼ保たれている状態です。通常は5~10年、平均6~7年で認知症に移行すると考えられています。
最近では治療薬の開発により、悪玉アミロイドの存在が確認されれば、治療ができるようになり、早期受診が認知症の状況の改善につながる時代になってきました。
まとめ
少しでも早期に受診して適切な治療やケアを早く始めることで、進行を遅らせたり、本人の希望にかなった生活に備えたりすることができます。認知機能の低下についての相談は、日頃から診ていただいているかかりつけの医師へご相談ください。
※インタビューの内容は趣旨を変えない程度に編集しています。
このページに関するお問い合わせ
福祉部 長寿福祉課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7819 ファクス:0594-86-7865
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地