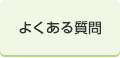いなべFM第106回令和7年6月27日放送「言語聴覚士の役割」について
いなべFM第106回令和7年6月27日放送「言語聴覚士の役割」

毎年6月4日から6月10日は「歯と口の健康週間」です。歯のみでなく、口くう及びその周囲の健康増進を目的としています。今回は、三重北医療センターいなべ総合病院リハビリテーション科言語聴覚士の一色志朗さんへのインタビューです。
「食べたい」思いに寄り添う摂食えん下リハビリ

言語聴覚士は、言葉によるコミュニケーションに障がいをお持ちの方や、食べ物の認識から、そしゃくして飲み込むまでの過程に障がい(摂食えん下障がい)をお持ちの方に対して、検査や評価を実施し、必要に応じて訓練・指導・助言・援助を行う専門職です。
例えば、摂食えん下障がいの原因には、次のようなものがあげられます。脳卒中による喉の機能低下や、加齢による喉や舌など口くう顔面周囲筋群の衰え、認知症により食べ物を認識しづらい、薬剤の副作用でえん下の力が弱くなるなどです。
まず、リハビリではえん下の力を強くする訓練を行います。次に、誤えんを予防するために食事の形態を工夫し、食べやすい姿勢や食事介助方法を提案し、安全に食事ができるように援助を行います。
口から食事がとれると、えん下に必要な機能を働かせることができます。また、口の洗浄効果や、味覚・そしゃくによる脳への刺激にもなります。さらには、食事を通して家族や友人との関係を築くことができ、生活の質を改善することが期待できます。
進行疾患によりゼリーの飲み込みですら困難になったAさんの事例を紹介します。
始めAさんは、「食べられなければ、死んだ方がまし。」とまで言っていました。摂食えん下リハビリチームの医師、看護師、理学療法士、作業療法士、管理栄養士が介入し、Aさんは摂食えん下リハビリに果敢に取り組まれました。ご家族の協力もあり、普通の食事を食べられるまでに回復されました。退院後にAさんと奥さんにお会いし、「今では何でも食べられます。あの時はありがとう。」と笑顔で話された時は、大変うれしく思いました。改めて摂食えん下リハビリは多職種のチームで協力することで、大きな効果が発揮できると認識した出来事でした。
まとめ
言語聴覚士の外来リハビリでは、疾患によるコミュニケ-ション障がいのリハビリ、末梢性顔面神経麻痺の治療、もの忘れ外来、脳卒中後遺症・交通事故・転倒などによる頭部外傷の方の高次脳機能評価や訓練などを行っております。お悩みの方は、かかりつけの医師へご相談ください。
※インタビューの内容は趣旨を変えない程度に編集しています。
このページに関するお問い合わせ
福祉部 長寿福祉課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7819 ファクス:0594-86-7865
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地