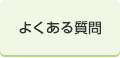いなべFM第87回令和6年9月13日放送「家族が認知症になった際の対応について」
いなべFM第87回令和6年9月13日放送「家族が認知症になった際の対応」

9月は世界アルツハイマー月間です。65歳以上の約7人に1人が認知症になると言われています。今回は、「家族が認知症になった際の対応」について、特別養護老人ホーム もも大安施設長、認知症看護認定看護師の島村真美さんへのインタビューです。
認知症の方を見守ることができるやさしい社会をつくること

認知症のはじまりの症状は人によってさまざまです。同じことを繰り返し聞いてくるなどといった症状から周囲の家族が気づき、医療機関を受診して認知症と診断されることが多いです。認知症の方と生活をしている家族からは、何回も同じことを聞いてきたり、何回言ってもわかってもらえなかったりすると、困惑や戸惑い、さらには怒りや苛立ちを感じる、頭ではダメだとわかっていても、つい口調がきつくなってしまう、などといった相談を受けることがあります。このような場合、家族は何ができて、何ができないのかを見極め、できることを続けてもらえるような声かけを勧めています。
例えば、洗濯物をたたむといった家事を行うことや、日記をつけるよう促す、などです。認知症になると、脳の細胞が壊れ、脳の機能が低下するため、物事を要領よくこなすことが困難になってきますが、タオルだけをたたむなど、具体的にわかりやすくお願いをするとできることがあります。日記も内容がうまく書けていなくても、何かを書くという日課や、家事の一部を担うという役割を持つことが、認知症の方の生きがいとなります。そして、支援で大切なポイントは、根気よく、何度でも、してくれたことに対して感謝することです。
認知症になると、自分ではできると思っていたことができなくなり、なぜできないのだろうかと自信をなくすと言われています。さらに、周囲からも、あれもこれもできなくなったと言われることが多くなり、二重の苦しみを体験しているそうです。そのような中で、自分で考えてできるということが自信となり、優しく接してくれる人が周りにいることで、認知症の方の安心につながります。たとえ時間がかかってもゆっくりで大丈夫、多少うまくできなくても大丈夫、と見守ることのできる優しい社会を地域の皆さまとともにつくっていくことが、認知症の方の支援において大切なことです。
まとめ
認知症の方は、自分が“忘れる”ということをとても不安に感じておられます。その不安が募れば募るほど、認知症が進んでいくこともあります。少しでも認知症の進行を遅らせるためには、その方が日々笑って過ごせるような日常生活を送れるようにすることです。そして、家族もひとりで抱え込まないで、医療や介護の専門家に相談して、助けを借りるたり、介護サービスを利用したりして、家族の負担を減らすことも必要です。困ったときはひとりで抱え込まず、積極的に医療や介護の専門家に相談してください。
認知症の方の医療や介護に関するお問い合わせは、
いなべ市地域包括支援センター 電話0594-86-7818までお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ
福祉部 長寿福祉課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7819 ファクス:0594-86-7865
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地