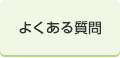最近の石榑の里 平成25年度
体育館の安全点検を行いました
2014年3月23日
3月2日(日曜日)体育館の安全点検を行いました。石榑小学校では日曜日の子どもたちの居場所づくりの取組として学校施設が開放され、石榑の里コミュニティがその管理を行っています。ボール遊びやロープ登りができる体育館は開放施設の中でも子どもたちに大人気です。その一方で様々な遊びが行われているため、危険箇所の定期的な点検が必要です。この日は、石榑の里コミュニティからはボランティア部会の各部長、学校からは教頭先生とコミュニティ担当の先生が参加し、体育倉庫や用具置き場を中心に点検を行いました。子どもたちが安全で安心して遊べるよう、これからも点検活動を続けていきたいと思います。

三重テレビの取材を受けました。
2014年3月9日
3月5日、三重テレビの取材を受けました。「みえの学力向上県民運動」の取り組みの一環で「地域ぐるみで学びと育ちの環境づくりを行います」のスローガンに沿った取り組みとして取材を受けたものです。「ワクワクスクール」の様子を主に、3年生の授業風景、校長・代表のインタビューと取材されました。来年度から検討している学習面の援助を取り入れた「ワクワクスクール」拡大は運動の趣旨に沿ったものだと思われます。なお、放送は3月21日22時15分からの「県政チャンネル」で放映される予定です。短い番組ですので少しの時間だと思いますがぜひご覧下さい。






学校のマネジメント力強化セミナーに参加
2014年2月23日
2月7日、文部科学省で開催された「学校のマネジメント力強化セミナー」に森代表が参加しました。セミナー第一部では、主催者挨拶の後、「コミュニティ・スクールの今後の展開 学校・家庭・地域の三者の協働体制の構築を目指して」と題して説明がありました。今、石榑の里コミュニティで取り組んでいる「放課後子ども教室」を全校区で展開する方針など興味深いものが多くあり今後の活動に活かしていきたいと思います。
第二部は、分科会で熟議が行われ、全国各地のコミュニティ・スクールに取り組んでいる学校との意見交換が行われました。これから取り組む学校・取り組んで日が浅い学校・長く取り組んでいる学校と様々でしたが、それぞれの悩み、解決方法など有意義な意見交換ができました。
日本経団連・21世紀政策研究所の視察を受けました。
2014年2月23日
2月19日、日本経済団体連合会・21世紀政策研究所、花原主任研究員の視察を受けました。目的は公共の建物などが地域にどのように使われているかの調査です。丁度、開催されていた石榑茶屋のモーニング・コーヒーを飲みながら、水貝校長・森代表が説明を行い、うまく学校と地域が地域ゾーンを中心に機能している仕組みを大変評価していただきました。その後、木をふんだんに使った教室、オープン教室、中庭、地域の人も入った工夫された校舎を見学され感心されました。

石榑ホールの窓拭きをしました
2014年2月17日
2月16日(日曜日)は地域と育友会が毎月一回、協力して学校を掃除する「地域清掃」の日でした。新校舎建設以来、「いつも、いつまでも、きれいな学校を!」と、清掃活動が続いています。この日は、石榑ホールの窓拭きを行いました。低い窓は子どもたちが、高い窓は地域ボランティアがというように、地域清掃では子どもと大人が役割分担や協力をしながら、一緒に掃除をして交流を図ります。冷たい北風が吹き付ける寒い日でしたが、きれいになった窓が澄んだ青空に映え輝いていました。

石榑モーニング 学習発表会でも大人気
2014年2月15日
1月25日(土曜日)の石榑モーニングは、学習発表会を見に来られた方で大賑わいとなりました。学習発表会に合わせて特別に開いたこの日、いつもとは違い家族連れの方が多く立ち寄られました。始めて訪れた親さんは「子どものたちの発表を振り返りながらコーヒーをいただきました。また機会があれば来たいです」と笑顔で感想を述べられました。この石榑モーニング。地域の目が子どもや学校へ常に注がれることで、安心・安全な学校環境を目指そうと取り組んでいます。2月28日(金曜日)まで、毎週月、水、金、午前8時から11時まで地域玄関入って直ぐの「石榑茶屋」で行っています。地域のみなさん、是非お越しください。

蝋梅の花が生けられました
2014年1月19日
石榑は一年で最も寒い時期を迎えました。そんな真冬に甘く優しい香りを漂わす花「蝋梅」が、石榑茶屋のホールに飾られました。生けられたのは、わくわくスクール「花あそび会」でお世話になる地域の先生。「石榑モーニングを訪れる方に季節を感じ、安らいでもらいたい」と、雪が積もった庭先からお持ちいただきました。蝋細工のように艶やかな花びらから漂う甘い香りが、訪れる人を心優しく包んでくれることでしょう。


韓国 教育・人間・環境 計測 研究室の視察を受ける
2014年1月19日
1月15日、韓国・東義大学校 柳教授を始めとする20名の視察を受けました。これは、東義大学校から依頼を受けた文部科学省が、全国の優れた学校施設の中の一校として石榑小学校を選んだものです。朝10時から約2時間半、いなべ市教育委員会近藤部長、水貝校長、石本建築事務所の説明を受けながら、意見交換や施設見学が行われました。名古屋大学 小松先生、伊藤教頭、森石榑の里コミュニティ代表、市教育委員会担当者も同席。学校の施設だけでなく、地域とのつながりや、地域住民も設計に参加してきたことなど、興味深く質問されました。校舎にちりばめられた色々な工夫にも感心、特に中庭の滑り台が気に入られたようでした。当日開いていた石榑モーニングのコーヒーも体験されるなど、「地域に開かれた学校」の取組にも興味を示されました。最後に石榑モーニングに来られていた、梅山さんから俳句を贈られ感激して帰途につかれました。


北海道東川町が視察・交流に訪れました
2014年1月4日
平成25年12月5日、6日、北海道東川町教育委員会と同町学社連携推進協議会の代表者ら6名が、石榑小学校を訪れました。平成26年度完成予定の東川小学校は、石榑小学校と同じように地域交流施設を併設、その運営を担うのが学社連携推進協議会の皆さんです。石榑小学校と石榑の里コミュニティの、学校と地域が連携した学校づくり、地域づくりを視察し、運営の参考にされることが訪問の目的です。
視察団の皆さんは、教育長への表敬訪問、石榑小学校の学校経営方針やコミュニティスクールの推進について校長との懇談、そして石榑の里コミュニティのメンバーとの交流や学校施設などの視察を精力的にこなされました。12月6日の早朝には「石榑モーニング」にも飛び入りされ、この日足を運ばれた地域の方とも熱心に懇談されました。
東川町教育委員会と同町学社連携推進協議会の皆様の熱心な取り組みにより、新校舎での学校・地域交流事業が順調にスタートすることを祈念しています。平成26年10月の開校が楽しみです。



居場所づくりに関する社会実験(地域ゾーンを活用したプチ・イベント)を行いました
2014年1月4日
平成25年11月18日から12月11日まで、高齢者や子育て世代などの居場所づくりに関する社会実験(地域ゾーンを活用したプチ・イベント)が行われました。
これは、石榑小学校の地域ゾーンを活用して、お昼間に高齢者や子育て世代の方、さらには広く地域の方々に来ていただき交流を深める、学校を拠点とした地域づくり推進調査事業の取り組みです。
たとえば「石榑モーニング」。朝8時から石榑茶で温かいお茶やコーヒーを用意しました。子どもたちの登校に同行されたその足で立ち寄られた方、散歩のついでに足を運ばれた方などが、子どもたちの元気な声が聞こえる中、石榑モーニングを運営する地域ボランティアらとの会話を楽しみました。その他にも地元の中国料理店の協力による「中国料理教室」、地域の囲碁名人による「囲碁教室」など、7つのプチイベントが延20回行われました。
期間中約150人の方が参加され交流を深めました。また、地域の方々の目が子どもや学校に注がれ、安心・安全の向上や開かれた学校づくりの推進が図られました。


学校を拠点にした地域づくりアンケートを行いました
2014年1月4日
平成25年10月、石榑小学校区の全世帯(約1700世帯)を対象に「高齢者の見守りと子育て・子育ち支援、および石榑小学校を拠点にした地域づくりに関するアンケート調査」を行いました。アンケート調査実施の周知、回収などにあたっては、自治会長様や自治会組長様にお世話になりました。ご協力ありがとうございました。アンケート結果については、名古屋大学小松研究室が分析し後日報告します。
学校を拠点とした地域づくり推進調査事業に取り組んでいます
2014年1月4日
名古屋大学小松研究室と石榑小学校学校運営協議会(石榑の里共育委員会)及び石榑小学校が連携して、学校を拠点とした地域づくり推進調査事業に取り組んでいます。この取り組みは、平成25年7月、総務省から同事業の採択を受けたいなべ市が、名古屋大学小松研究室に委託し進められているものです。
具体的には平成25年9月から平成26年3月に掛けて、(1)石榑小学校区全ての世帯を対象に高齢者や子育て・子育ち支援などに関する住民意識調査、(2)高齢者や子育て世代などの居場所づくりに関する社会実験、(3)社会実験の検証と学校を拠点とした地域づくり調査のとりまとめ、(4)同調査事業の報告会の開催、などが行われることになっています。
秋の登山を行いました
2013年11月20日
11月2日(土曜日)、恒例となった登山を行いました。校歌にも歌われている「竜ヶ岳」に親子で登ろうと始められたこの取組は、今回で4回目を迎えます。金山尾根を登るコースでは、ところどころで色づき始めた木々が現れると、立ち止まっては写真に収めました。この日の山頂は11月始めにしては気温が低く、お昼も早々に切り上げ下山しました。遠足尾根を下るコースでは登山者もあまり通らない大日向の三角点(696m)を通りました。宇賀渓観光協会や山岳会の方々のご支援により、今回も安心して安全に登山ができましたことに心より感謝申し上げます。



石榑の里まつり 大成功!
2013年11月20日
11月10日(日曜日)、石榑の里まつりが開催されました。地域と学校が、子どもと大人が、力を合わせて企画し運営するこの取組は、今回で7回目を迎えます。今年テーマは「石心でつなげよう!地域の絆」。「石心」とは、子どものため、学校のため、地域のために力を尽くすることをいとわない石榑の人々の心のことです。明治40年(1907年)の学校設立以来、石榑の地に脈々と流れるこの石心により、いい学校、いい地域を築いていこうというものです。当日はあいにくの雨にも関わらず沢山の方にお越しいただき、各所で交流が行われました。毎年参加されるという高齢のご夫婦は「毎年楽しみにしている。孫が小学校を卒業しても参加したい」と児童の元気な様子を眺めながら語られました。また、来年石榑小学校に入学予定の子どもを持つお母さんは「始めて参加した。パパさんバンドの演奏にあわせて歌う子どもたちの姿に感動した」と感想を聞かせていただきました。

庭園の剪定をしていただきました
2013年9月29日
9月29日(日曜日)、小学校の庭園にある松の剪定をしていただきました。お世話になったのは、松の剪定を得意とされる地域のボランティアの皆さんです。1975年(昭和50年)、鉄筋校舎の建設にあわせて造園業などに携わる地域の方の無償労働によって造られた庭園。毎年きれいに整備していただくおかげで、昭和の校舎の思い出がしっかりと引き継がれています。


石榑小学校運動会
2013年9月29日
9月28日(土曜日)、学年縦割りチームの意気込みを掛け声で表現した開会式で運動会は幕を開けました。
徒競走では、全児童が自己ベストタイムを目指し最後まで全力で駆け抜けました。妖怪に変身した児童の七変化がバッチリ決まった1-2年生の「歌舞伎たいそう いざやカブかん!」。島唄の曲に合わせ沖縄民舞エイサーを石榑バ ージョンで踊り切りった3-4年生の「石榑エイサー」。雄大にそびえる竜ヶ岳を見事に表現した5-6年生の組立体操「頂・竜ヶ岳」。全校児童281名が1か月間の練習成果を存分に発揮した見事な演技に、大きな拍手が送られました。
お昼休みには、恒例の「石榑小唄」を、大人と子どもが幾重もの輪になって踊り、地域全体で運動会を盛り上げました。
秋晴れのもと、児童の頑張りとそれを支える先生方、そして児童の一挙手一投足に声援を送る観覧者の思いが一つになった素晴らしい運動会でした。


石榑の里まつり第2回実行委員会・新企画登場!
2013年9月21日
9月13日(金曜日)、第2回目の実行委員会が行われました。夜7時30分からの開催にもかかわらず約90人の実行委員が参集しました。
第一部の全体会は、前回(8/23)の検討概要の報告とタイムスケジュールの提案です。“ゆるキャラ”石心(いしころ)くんの登場や、来場者が催しをゆっくり回れるよう午前の部を30分延長して12時30分とすることなど、新しい取組や改善工夫が報告・提案されました。
第二部は各部会に分かれて催しの検討です。展示部会では、新企画「石榑の道標やお地蔵さんを探そう!」という“地域探検・児童参加型”の取組が検討されました。今年の里まつりも大いに期待できそうです。


北海道東川町学社連携の取組に学ぶ
2013年9月13日
8月26日(月曜日)から28日(水曜日)にかけて北海道東川町教育委員会を訪れました。建設中の東川小学校に併設される地域交流センターを活用し、子どもから高齢者まで多様な世代への学びの場の提供を担っていこうとする「東川町学社連携推進協議会」との交流が目的です。
建設中の新校舎を拠点に地域ぐるみでの学校づくり、子どもも大人も共に学び育つ環境づくりを目指す東川町の取組。石榑の里コミュニティとの共通点も多く、双方にとって有意義な交流になるはずだと、北海道大学の小篠先生と名古屋大学の小松先生のコーディネートで実現したものです。
北海道の雄大な自然のなか、農業、食、環境、アウトドアなどの地域資源を活かした多様なプログラムと、これを運営していくための組織体制など、石榑の里コミュニティが学ぶべきことは多く実りある交流となりました。


石榑の里まつりにむけキックオフ! 第1回実行委員会
2013年9月13日
8月23日(金曜日)、午後7時30分から石榑の里まつり実行委員会が開催されました。毎年11月、石榑小学校を会場に地域住民や子どもたちらの企画・運営により行われるまつりは今年で7回目を迎えます。これまでの取組により「地域と学校のつながりが強まった」「感謝の気持ちや石榑の誇らしさを感じるようになった」という感想が年を重ねるごとに増えてきています。
この日は、実行委員約90人が石榑ホールに集い、まつりの骨子や予算などを確認したり、分科会に分かれて各催しを検討したりしました。次回の実行委員会は9月13日(金曜日)午後7時30分から開催されます。


皆で学校をきれいに!学校清掃
2013年9月8日
9月8日(日曜日)学校清掃が行われました。石榑小学校の素晴らしい環境は「いつも」「いつまでも」きれいでありあたいと、学校、育友会、ボランティア環境部会が協力し合い、新校舎建設以来、原則毎月第3日曜日の午前9時から実施しています。
この日は、4年生の親子ら約50名が雨の合間を縫って中庭で、草取り、ウッドデッキやタイルの磨き上げなどを行いました。掃除終了後には恒例の交流会が開かれました。短い時間ではありますが、お茶とお菓子を前に日頃なかなか話すことができない人との会話が弾みました。次回は10月20日(日曜日)午前9時からの予定です。


「全国コミュニティ・スクール研究大会in京都」に参加しました
2013年8月16日
7月30日(火曜日)、「全国コミュニティ・スクール研究大会in京都」に参加しました。文部科学省が進める「地域とともにある学校づくり」の方策を協議・研究するため、全国の教育関係者らが国立京都国際会館に集いました。
大会前半では「京都市名誉市民表彰式」が合わせて開催され、ノーベル賞受賞者の山中伸弥教授が表彰されました。記念スピーチでは「子どもたちのユニークな発想を伸ばしてほしい。アイデアを否定するのではなく、やらせてみることが大事」と語られました。
続いて、元日本アイ・ビー・エム株式会社社長 北城恪太郎氏の「今後の我が国の教育に期待すること」と題する記念講演、中野津市教育長などによる教育長リレー討議、地域の学校支援や中小連携などの先進的な取組を行う学校などの実践発表がありました。

石榑の里まつり事務局会を開催しました
2013年8月16日
8月9日(金曜日)、石榑の里まつり事務局会が開催されました。この日は8月23日(金曜日)に開催予定の第1回石榑の里つり実行委員会の提案議題について協議を行いました。今年も「観る」、「遊ぶ(作る・体験する)」、「食べる」の3本柱のもと、「地域の方の作品展示」、「次世代へ伝えたい遊び」、「お昼の食事」など、17の催しが提案されることになりました。今年で7回目となる「石榑の里まつり」は、“石心でつなげよう地域の絆”をテーマに、11月10日(日曜日)に開催されます。

「わくわくスクール」拡大検討プロジェクト会議開催
2013年8月10日
平成25年7月28日(日曜日)、今年度4回目となるプロジェクト会議が開催されました。
「わくわくスクール」は、平成16年に新校舎の完成に合わせて開設され、野に咲く花を生ける「花あそび会」や、親子でおやつ作りを楽しむ「作って食べよう」など、地域住民による様々な体験教室を通して、子どもたちが健やかに育まれる環境や、放課後の子どもたちの安心な居場所を提供してきました。
平成24年10月、石榑の里共育委員会(学校運営協議会)で、7年間の実績と成果を踏まえ「わくわくスクール」の拡充に向け検討を行うプロジェクトの設置が承認され、これまで、先進地視察やニーズ調査アンケートなどが進められてきました。
この日は、わくわくスクールの拡充案として、学習支援、スポーツ、文化などの教室を設けることが検討されました。


伊丹東中学校「ファミリーサポーターズ」を視察しました
2013年7月20日
7月12日(金曜日)、13日(土曜日)、兵庫県伊丹市立東中学校の、地域と学校と家庭が協力して子育てをする「東中ファミリーサポーターズ」の活動を視察しました。東中ファミリーサポーターズは、先生が授業や部活動に注力できるよう、地域やPTAなどが校内の掲示装飾や樹木の手入れ、図書活動や学習支援などを行うボランティア組織です。
この視察は、東中ファミリーサポーターズと石榑の里コミュニティが、こころを育む総合フォーラム主催の「子どもたちの“こころを育む活動”」全国大賞を受賞(東中:2012年度、石榑:2011年度)したことで実現したものです。
今回は、毎月2回土曜日に同校を卒業した大学生や高校生、地域住民の元校長や元先生らがサポート役となって、生徒に学習習慣をつける「スタディーサポート(サタスタ)」の活動を中心に、その取組を学びました。また、サタスタの運営や仕組などについて、学校長や団体のリダー、PTA役員らと交流を行いました。
こころを育む総合フォーラムのHPにも紹介されました。



海外支援衣料回収を行いました
2013年7月20日
6月15日(土曜日)、海外支援衣料回収活動を行いました。株式会社デンソーのボランティア組織「デンソーハートフルクラブ大安」の協力のもと、石榑小児童会、育友会、石榑の里コミュニティが実施し、今年で4年目を迎えます。
児童たちは、衣料不足などで困窮する発展途上国への海外支援活動の意義や目的について理解を深めるため、5月に株式会社デンソーの社員から事前講義を受け、回収活動に臨みました。
集まった段ボール30箱分の衣料と、募金20,950円は、児童らの手で株式会社デンソーハートクラブに手渡され、日本救援衣料センターを経てミャンマーとガーナへ送られます。


「国道の草刈り」を実施しました
2013年6月8日
6月8日(土曜日)、毎年恒例の国道の草刈りを行いました。地域の区長さん、民生委員さん、育友会、地域ボランティア、小学校職員など、40人を超える方々に参加、協力いただきました。
この事業は、三重県から業務を受託し、受託料をコミュニティの活動資金に充てています。地域の中央を走る幹線道路であり、児童の通学路でもある道路がきれいになり、環境の美化と交通の安全確保もでき一石二鳥です。

「作って食べよう」開催しました (わくわくスクール)
2013年6月8日
6月2日(日曜日)、指導伝承部会が行う「わくわくスクール」の一つ「作って食べよう」が行われました。親子22名が参加して、わらびもちと、バニラジェラートを作りました。親子でこねたり、混ぜたり楽しく活動しました。これからの暑い夏にふさわしい、涼しいデザートが出来上がりました。

竜ヶ岳登山を実施しました
2013年6月8日
平成25年5月18日(土曜日)、5,6年生の児童およびその親と竜ヶ岳(1099m)に登りました。校歌にも歌われている地域の山に登ろうと昨年から始まったこの企画は、今回で3回目を迎えます。同行支援をいただいた山岳会の方に登山道に咲く花を見つけては、カタクリ、イワカガミ、山ツツジなどと一つひとつ名前を教えてもらいました。8合目付近では可憐な白い花を咲かせるシロヤシオに出会うことができました。好天にも恵まれ参加者は春の竜ヶ岳を満喫しました。


石小ぼちぼち応援団を開催しました
2013年5月11日
4月20日土曜日、石榑小学校くつろぎの間で、ぼちぼち応援団交流会を開催しました。この応援団は「出来る人が出来る時に、子どもや学校を息長く応援する」を合言葉に平成24年4月に結成されました。
この日は、「応援してほしいこと」、また「応援できること」等、学校と応援団がきたんのない意見をかわしました。支援の輪が更に広がりそうです

地域・学校交流会を開催しました
2013年5月11日
平成25年4月20日 石榑小学校 地域会議室にて先生と地域の交流会がもたれました。新体制になった教職員とボランティア部会役員との顔合わせをおこないました。
交流会は各自の趣味や抱負を自己紹介し、なごやかな雰囲気ではじまり、よりよい学校づくりに向けて、意識を高めることができました。

PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
石榑の里コミュニティ
電話:0594-78-0002 ファクス:0594-78-1949
〒511-0266 三重県いなべ市大安町石榑南611番地(石榑小学校内)